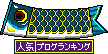2011年02月05日
木曽義仲の軍師・覚明の古筆切

紙本肉筆/古筆手鑑崩し古筆本家極札添付
木曽義仲の軍師大夫坊覚明筆 平安末期
覚明(かくめい)
生年: 生没年不詳平安末期・鎌倉初期の僧。
元は興福寺の学僧。出生は海野氏の生まれだと言うのが一般的です。以仁王が平家打倒のために立ったとき、園城寺は興福寺に宛てて以仁王の味方するように要請する文を出しました。その返牒を興福寺が出した際に、信救(覚明)にその執筆を頼んだという事です。信救は「清盛は糟糠、武家の塵芥」とののしり、ともに戦うことを約束しました。糟糠とは「かす」や「ぬか」のことです。塵芥はごみとあくた。まったく武士として価値がないということです。平家にあらずんば人にあらず、というくらい奢っていた清盛に、その手紙の内容も結局そっくり伝わったものですから、大変です。さすがに、激怒した清盛は挙兵し、以仁王を攻撃。信救も兵を連れて以仁王の援護に向かいますが、到着する前に以仁王は戦死し、信救も追われる身となりました。興福寺にいられなくなった信救は顔に漆を塗って人相を変えて信州に逃亡します。美ヶ原温泉の湯で顔の療養をしたとか。それから、太夫坊覚明と名をかえました。その逃亡途中で源行家と出会い、ともに頼朝のもとに行きますが、行家は頼朝と仲たがいをして、結局信濃の国府松本にいた義仲のところに向かうことになりました。そこで若き武者義仲と出会います。覚明は、博学と文才をもって義仲の祐筆(書記)として仕えることになります。以後は武勇の将ばかりの中で義仲軍の頭脳、軍師として活躍します。倶利伽羅峠での戦いの前には木曽願書(戦勝祈念文)を書き八幡宮に納めました。また、入洛する時には比叡山を味方につける「木曽山門牒状」などを書いて、まさにペンは剣より強しの実例をつくりました。ただ、入洛後に彼はいつ間にか姿を消しています。平家を倒すという目的を達したので、名誉地位などには関心がないということかもしれませんし、義仲と仲違いしたのかもしれません。覚明の去った後は、義仲は負け戦ばかりでしたので、名軍師は、やはり大事にしなくてはなりませんね。その後、様々な伝説を有しますが、その文才を生かして活躍したことは事実です。義経記の製作にも関わっているとされ、曽我物語、平家物語などの作者ではないかともいわれています。
義仲ブームが次第におきそうな気配です。
もちろん義仲とか主役級に人気が集まりますが、その軍師、日本の諸葛亮孔明とも言える覚明もお忘れなく。