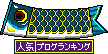2011年06月30日
揺れた市街地 直下型地震の脅威

市民タイムス号外 6月30日
地震もさすがに人事ではなくなって来ました。
今朝8時16分 松本市震度5強。
20~30cmくらい乗っている車が波に揺られるようにぐあんぐあんと揺すられました。
橋の横の信号機が30秒たってもまだ大きく風柳のように揺れていて気持ち悪かったです。
余震もあり生きた心地がしません。
子供たちも一端校庭に避難した後、ひとまず下校となりました。

コンクリートのブロック塀があちこち倒れていました。
通学時間でなかったのが救いです。

石垣も。

中に鋼が通っていないのは、手抜き工事ではなかろうかと思います。

ただブロックを乗っけただけの塀の場合は簡単に崩れてしまいます。

門柱もたおれていました。

屋根の瓦が踊ってしまう家がたくさんありました。

応急処置でブルーシートなど被せます。
まだ余震が続いていますので、修復は地震活動が終息してから。

あれだけの揺れがあるとどこかこうか家の中も歪みがありそうです。金魚もビックリ。

トイレのションベン小僧も倒れていました。

立ち上がれJapan、がんばれ日本!ションベンをかけられたカエルの様に、たとえ何が起きても動じるな!
そして、早くカエルこと。

タグ :地震
2011年06月29日
地震 中信地区揺れる

地震がいよいよ中部地方内陸でおき始めたのか、3回ほどドドッと夜揺れましたね。
震源地は中山。牛伏寺断層。フォッサマグナ、、、。
玄関のリースが落ち、小さい置物が床に落下して壊れてしまいました。

先日の上高地の土石流といい、災害の予兆でしょうか。
写真をとっておけばよかったですが、六時半頃中山付近に夕方巨大な入道雲が一つだけ不気味にモクモクしていました。普通は、出来る場合は複数出来るものですが、一つだけというのが変でした。
皆さんも、雲に注意してみてください。不気味な予兆があるかもしれません。
2011年06月28日
世界自然遺産となった小笠原諸島とアホウドリ

写真はiPhone無料アプリBonin Islands Clockより
江田五月環境大臣は、小笠原諸島の自然遺産への登録について「震災の苦しみの中、大変勇気づけられることだ」と述べました。そして「小笠原は生物進化の縮図と言われる場所で、世界的な価値が認められたということ。こういう感情、震災の苦しみの中で私どもにとって大変勇気づけられることだ」と。
小笠原諸島(おがさわらしょとう)は、東京都特別区の南南東約1,000kmの太平洋上にある30余の島々です。日本の国土で、東京都小笠原村の区域。総面積は104km²。南鳥島、沖ノ鳥島を除いて伊豆・小笠原弧の一部をなしています。
1593年(天正20年)信濃国深志(松本城)城主の小笠原貞頼が発見したといいます。1727年(享保12年)小笠原貞頼の孫にあたる小笠原貞任が貞頼の探検事実の確認と島の領有権を求めて幕府に訴え出ました。小笠原島と呼ばれるのはこれ以降のこと。最終的に貞任の訴えは却下され探検の事実どころか先祖である貞頼の実在も否定されてしまいました。このため、貞任は1735年に詐欺の罪に問われ、財産没収の上、重追放の処分を受けたのです。小笠原氏はさんざんでしたね。今、400年余の時を経て、小笠原の名が世界遺産となり報われたかもしれませんね。

小笠原諸島のアホウドリ
アホウドリというのは、羽毛布団の材料として狙われ、のろまで人間をすぐに信じ簡単に捕まってしまうからだそうです。小笠原氏のようにさんざんな目に合ってきたんですね。「信天翁」、「沖の太夫」とも言います。
学名はDiomedea albatrusといい、英語でalbatross、「アルバトロス」。ギリシャ伝説の英雄の名に由来します。この英雄アルバトロスは死後、南イタリアの沖の小島に葬られ、海鳥になったと信じられました。欧米では、この鳥が羽ばたくことなく何時間も洋上を飛翔する姿から「美しい海の女王」をイメージしたそうです。
是非、小笠原諸島でこの勇姿を観てみたいものです。また、ゴルフで「アルバトロス」(パーより3つ少ない)をぜひ、、、、これはムリで賞。


by osomatsu's fotolife
http://f.hatena.ne.jp/osomatsu/
私の友人が、ある企業で何でもいいから研究しろ、、という仕事を頂き、小笠原諸島にはなぜ美人が多いのか、ということを調べてレポートしたということを聞いたことがあります。
是非、その研究対象を観にも行きたいものですね。(アホウ!
 )
)
2011年06月27日
岳(ガク) 作者石塚 真一

映画「岳」の原作であるコミック版「岳」は、山登りが大好きな作者石塚真一の登山へのいざない。読んでいるだけで、沢山の山に登ったような気がしてきます。
ウィキペディアによる紹介文によると、
石塚 真一(いしづか しんいち、1971年 - )は、日本の漫画家。茨城県出身。
プロフィール
アメリカの南イリノイ大学、同国サンノゼ州立大学在学中にロッククライミングの虜になり、日本に帰国後、その経験を元に『岳 みんなの山』を描き始める。2001年、『This First Step』で、第49回小学館新人コミック大賞一般部門に入選。『岳 みんなの山』で、2008年3月に第1回マンガ大賞を、2009年1月に第54回(平成20年度)小学館漫画賞一般向け部門を受賞した。
アメリカでは、気象について学んでいた。帰国後に勤めた会社が約1年で倒産したという苦労人でもある。
5年間アメリカに留学中だった頃から、漠然とマンガを描きたいとは思っていたそうであるが、帰国して、実際に描き始めたのは28歳の時からであった。「340円で、マンガの描き方の本を買ってきて始めた」。
なお、石塚が好きな場所(山)は、アメリカのワイオミング州、グランド・ティトンとのこと。
以上
好きこそ物の上手なれといいますが、趣味を高じることも才能を開花させる上で必要かもしれませんね。
前出記事:映画『岳(ガク)』 生死の極限 救世者たち
2011年06月26日
高速増殖炉「もんじゅ」は、どんな「もんじゃ」

ときどき家で「もんじゃ焼き」を作るのが、正しい作り方なのか分からないので一度お店で食べようと「がじゃもんや」へ出かけました。いつもは、お好み焼きとかはうちで作って食べた方が安上がりということで外では食べないので、初めてのことです。
すると、このお店は土日は家族連れで来る方は半額のメニューがあるという事実を知り、なんだそれじゃ外で食べた方がいいねということに気付きました。意外と試してみないと分からないものですね。
もんじゃ焼きは、モチとかチーズをいれると美味しいんですね。
もんじゃ焼きの前出記事:エコな生活③
http://ikiikiikiyou.naganoblog.jp/e762874.html
:もんじゃ焼き
http://ikiikiikiyou.naganoblog.jp/e684009.html

ここのお好み焼きは、軟らかいですね。

休みの今日もバスケの練習をしてきた子供たちは、食欲旺盛です。
がじゃもんや 松本笹賀店 長野県松本市大字笹賀7325-1
TEL0263-85-0840
「もんじゃ」と似ていてややこしいですが、「もんじゅ」の話。
敦賀市の高速増殖原型炉「もんじゅ」で24日、昨年八月から原子炉容器内に落下したままだった燃料交換用機器の引き抜き作業が完了し、日本原子力研究開発機構の関係者らは、一様にホッとした様子を見せたといいます。引き抜きには過去2度失敗し大騒ぎしているだけに一安心です。国の核燃料サイクル政策の中核である「もんじゅ」は、本年度中の40%出力試験実施と2013年度中の本格運転を予定していますが、落下事故の影響や福島第一原発事故で国の原発政策に風当たりが強くなる中、先行きが不透明となっています。この際、やめちゃった方がよいのでは?

取り出した燃料交換用機器が入った伸縮式の大型密閉容器=24日午前5時ごろ、敦賀市のもんじゅで(写真は日本原子力研究開発機構より)
「もんじゅ」は、以前、日本の核武装計画が外交文書で明らかになった高速増殖炉です。
⇒核開発をリンクさせて国家が取り組んでいたことがばれた内容pdf
本当に、核開発をしたいのなら、堂々と国民に了解を得てからにしてほしいですね。(得られるかどうかは別として)
1990年に設立された市民グループ「ストップ・ザ・もんじゅ」の提言
http://www.page.sannet.ne.jp/stopthemonju/
日本の核武装化に手を貸し、原子力産業を潤し、ごく一部の人々を養うだけの高速増殖炉開発。この愚かな政策は即刻中止すべきです。この「核」開発に向けられる予算を自然エネルギー立国に向けて振り向けられれば、遙かに有意義な結果が得られるでしょう。
「もんじゅ」は文殊菩薩(もんじゅぼさつ)から来ている名前だそうです。一般に智慧を司る仏とされています。
日本の夢と消えた「満州」。これも文殊菩薩からきています。建州女真族の本尊とされ、その名にちなみ満洲(満州)と自称。ホンタイジ以降、全ての女真族の呼称に代え満洲族と呼称するようになりました。したがって満州の名は文殊が語源であるとされています。「もんじゅ」という名前に日本の過去に消えた幻の大陸「満州」の面影、夢を日本のエスタブリッシュメントたちは見ているのでしょうか。
NSP 面影橋
http://youtu.be/_HaVsK0ez2g
堀内孝雄の新リリース「面影橋」もいいですが、NSPの曲も懐かしいですね。
使う使わないは別として、確かに、米国の属国状態から本当に自立するためには核兵器は必要かもしれません。三島由紀夫は、死ぬ前にはっきりと核兵器は、他の先進国と対等の立場になるためには持つべきだと言っていました。
被爆国としては、避けたい武器ですが、完全な自衛対策ということで。いずれにしても戦争放棄が原則ではあります。でも、第三次世界大戦に巻き込まれていく危険性はあるのでやはり止したほうがいいと智慧のある文殊菩薩なら言うでしょう。
2011年06月25日
堀内孝雄コンサート 白虎隊精神は今も健在 東北ガンバ!

堀内孝雄の民音コンサートが松本市文化会館でありました。
新曲「面影橋/時の流れに」をこの春発売していますが、元気に何曲も歌っていただきました。
面影橋というのは、都営交通荒川線の早稲田駅の次の駅だそうです。
今年は、都営交通100周年でイベントが開催されますので、関連で是非多くの方に聴いてもらえればいいですね。
堀内孝雄公式サイトhttp://www.takao-horiuchi.com/
http://youtu.be/Nd61zroOaUQ
愛すべき男たち
堀内孝雄自身も愛すべき男ですね。公演後握手していただき感動しました。
一曲ごとにありがとう、サンキュー、と感謝を込める姿勢が素晴らしいです。
かみしめるように歌う表情もよかったです。途中オペラグラスで観ていたら、歌う世界に引き込まれました。
「愛しき日々」堀内孝雄
http://youtu.be/abdoobSe3kg
「愛しき日々」といえば、白虎隊ですね。
日本武士道精神の美しさを歌った名曲です。
動画コメントより
今回の震災では、会津白虎隊隊士自決した中での只一人の生き残り飯沼貞吉さんの末裔が宮城の病院で、医師として避難民の救済の為に、獅子奮迅の働きをされています。 また、同じく会津藩士を祖に持たれる秋篠宮妃殿下の弟さんが、偶然相馬で震災に遭遇、難民救済のリーダーとして活躍されており、両人を数学者藤原正彦が週刊新潮で会津武士の発露と絶賛しておりました。
PRPS3603
白虎隊 Japanese sad story. This is 『Aizu spirit!』
http://youtu.be/MAxHrsEXDXA
白虎隊とは:ウィキペディアより引用
慶応4年(1868年)、鳥羽・伏見の戦いにより戊辰戦争が勃発した。会津藩は旧幕府勢力の中心と見なされ、新政府軍の仇敵となった。会津軍の劣勢は如何ともし難く、少年兵で組織された白虎隊も各所で苦戦を強いられた。なかでも最精鋭とされた士中隊も奮戦空しく撤退を余儀なくされた。このうち一番隊は藩主・松平容保護衛の任に当たったが、二番隊は戸ノ口原(戸ノ口原の戦い)で決定的打撃を受けて潰走し、戦死者も少なからずあり、負傷者を抱えながら郊外の飯盛山へと落ち延びた(この間、庄田保鉄ら隊員数人が農家で草鞋を貰い受けている間にはぐれた)。だが、ここから眺めた戦闘による市中火災の模様を、若松城が落城したものと誤認して悲観、その結果総勢20名が自刃を決行し、一命を取り留めた飯沼貞吉(のち貞雄と改名)を除く19名が死亡したとされているが、事実は若松城が落城したと誤認して悲観したのではない。飯沼貞吉が生前に伝え残した史料によれば、当時隊員らは鶴ヶ城に戻って敵と戦うことを望む者と、敵陣に斬り込んで玉砕を望む者とのあいだで意見がわかれ、いずれにせよ負け戦覚悟で行動したところで敵に捕まり生き恥をさらすことを望まなかった隊員らは、城が焼け落ちていないことを知りながらも会津武士らしく飯盛山で自刃を決行した。
途中はぐれた庄田保鉄らはその後、鶴ヶ城に入城し、士中一番隊の生存者と共に白虎士中合同隊となって西本丸を守った。籠城戦は1ヶ月続いたが、最終的に会津藩は降伏した。
その後、飯沼貞吉は電信技士として維新後を生き抜き、1931年に79歳で没した。飯盛山での出来事についてその重い口を開いたのは晩年だったそうで、そこから白虎隊の最期の様子が現在に伝わった。ちなみに、日清戦争時に電信技師としてソウルに渡った際にピストルを携帯するように言いつけられたが、「自分は白虎隊として死んだ身である」と断ったという逸話が残っている。同じ「士中二番隊」の隊士であった、酒井峰冶(さかいみねじ 1851年 - 1932年)の手記が近年発見された。酒井も生前、当時のことは家族にもほとんど話さなかったそうである。飯沼の遺骨の一部は、遺言により飯盛山に眠る同志と同じ場所に埋葬された(但し、飯沼の墓は他の隊士の墓から距離を置いて建てられている)。
あくまでも予備兵力であったために実効的な火力を持ちえなかった事から、実際の戦局への影響力はさしたるものではなかった。しかし、構成員が少年ばかりであったこの隊が、終始一貫して組織的な戦闘行動を取れていたことは特筆に価する。反面、その最大の長所が却って隊員の意識の硬直化を促進し、悲劇的な最期に繋がったのではないかという説も根強い(仮に彼らに現実的な発想があり、かつ柔軟な対応が取れていれば、城で戦う友軍が敵の攻撃に持ち応えている可能性を考慮し、少なくともその場で全員自刃はしていなかったであろう)。
以上
東北の人たちの今回の大震災の際の勇気と辛抱強い戦いぶりは、白虎隊にもつながる代々の武士道教育が受け継がれているからでしょう。
2011年06月24日
りんどう会 総会

くろよん観光取引業者の親睦会りんどう会の総会が開かれました。

88社加盟。くろよんロイヤルホテルで乾杯。

中国の方が原発以来激減していましたが、増えてきているようです。

新緑回廊。
大雪回廊→前出記事:黒部立山アルペンルート 大雪の閉山
http://ikiikiikiyou.naganoblog.jp/e616033.html
タグ :りんどう会
2011年06月23日
キャロの近況

キャロは、最近どうですか。
と安否を聞かれることがありますので、近況報告しましょう。
上記写真は長女ライが撮影したものです。

数ヶ月肥えて2kgに王手をかけていましたが、このところ早くも夏バテか1.7kgに戻ってしまいました。
梅雨の時期は、気分がちょっと乗りません。
お休み中です。
2011年06月22日
辰野ほたる祭り

辰野ほたる祭りが最盛期です。
写真家の先生に今日は連れてきて頂きました。
なかなか真っ暗い中どうやって撮影すればよいかよく分からない状態でしたが、1500匹あまりの蛍が舞う幻想的な光景に初夏の風物を満喫できました。

なんで光るのでしょう。

辰野は、蛍が主役ですね。
蛍は、自家発電で光ります。エコな昆虫ですね。
蛍は人の気配にも逃げるということはなく、とても人懐こい昆虫です。
亡くなった人が蛍火になって飛び交うという話しはあながち外れていないかも。
参考前出記事:神風特攻隊の夢 壮絶大西瀧治郎 憂国三島由紀夫
「死んだらまた小母ちゃんのところへ、ホタルになって帰ってくるよ」と言い残して宮川三郎軍曹は鹿児島県知覧基地から出撃していきました。そして不思議なことにその夜、トメの家に本当に一匹のホタルが入ってきたといいます。
映画『火垂るの墓』
http://youtu.be/0PEURA6Y1CM
この映画原作を子供の頃マンガで読んで、泣いた泣いた。
ドラマ版「火垂の墓」
http://youtu.be/HjfjSXmibtI
感動のストーリーがこれだけでも分かりますね。
福山雅治 「蛍」 (Full ver.) PV
http://youtu.be/pb4ay9SVQeo
名曲ですね♪
タグ :蛍
2011年06月21日
信州そば道20 レストハウス木曽路

木曽のそばは、色が黒くていかにもそばらしい趣があります。
ここは、レストハウス木曽路。木曽路きってのドライブインです。なぜかというとここは国の名勝に指定されている寝覚めの床の真上に位置していて、食事をしながら絶景が観れるのです。

朝の連続テレビドラマ「おひさま」で番組の終わりに長野県の景勝地紹介として寝覚の床が出ていました。奈良井宿などロケにも使われていて木曽も観光客が増えています。
ここは、木曽川の水流によって花崗岩が侵食されてできた自然地形です。かつては急流でしたが、上流に設けられた木曽ダム(1968年に運用開始)などにより水位が下がったため、水底で侵食され続けていた花崗岩が現在は水面上にあらわれています。水の色はエメラルドグリーン。子供の頃からよく電車でこの横を通る際にエメラルドグリーンがチラッと見えて、うとうと寝ていたのがパッと目が覚めますね。
長野県歌「信濃の国」の4番にも「旅のやどりの寝覚の床」とうたわれています。
寝覚の床の中央にある「浦島堂」は、浦島太郎が弁才天像を残したといわれています。
浦島太郎伝説のなかで寝覚の床には、浦島太郎が竜宮城から帰ってきた後の伝説が残っています。
浦島太郎は竜宮城から地上へ帰りましたが、まわりの風景は変わっていて、知人もいないので寂しくなり、旅に出ることにしました。旅の途中、木曽川の風景の美しい里にたどり着き、竜宮の美しさを思い出し、乙姫にもらった玉手箱をあけてしまいます。玉手箱からは白煙が出て、白髪の翁になってしまいました、とさ。
浦島太郎には、今までの出来事がまるで「夢」であったかのように思われ、目が覚めたかのように思われたのでしょう。このことから、この里を「寝覚め」、岩が床のようであったことから「床」、すなわち「寝覚の床」と呼ぶようになったといいます。
芭蕉の句に「義仲の寝覚めの山か月かなし」という句があります。芭蕉も寝覚を通っているので、ファンであった義仲を木曽路で偲んだことでしょう。句碑をぜひ建ててみたらと思います。