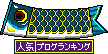2010年06月07日
上田城 日の本一のつわもの 真田一族

パーマン6号です。ではなく、、、真田幸村の兜のイメージです。
「赤備え守り兜」です。直径2mあります。
上田城公園にあります。
上田城は、真田氏が築いた城で、真田氏は40年間の統治の中で、2度も徳川の軍勢を撃退しています。最初は、1585年、7千人余の徳川軍撃退。二回目は、1600年に3万8千人の徳川秀忠軍を退けました。
小さな平城なのに、どうしてここに籠城して、勝てたのでしょう。

城内には、このような井戸があり、抜け道がありました。食料確保に役立ったと思われます。このような知恵がある武将が真田一族なんですね。

西櫓。

堀は、石垣ではなく掘っただけです。

真田石と呼ばれる長いところは3mあるという大石。

歴士、歴女。今、着物を着て、ジャパン観光するのがブームなんですね。

上田城主松平氏の武具。博物館展示。
昔、剣道をしていた私は、武具をみるとドキドキします。

真田一族の人形。
参考真田幸村 前出記事:http://ikiikiikiyou.naganoblog.jp/e432343.html
戦国バサラ 真田幸村 第一章 死守!武田、上田城!ゲームの世界でも真田氏は人気ですね。
http://www.youtube.com/watch?v=zEFo8TBnSIM
私は、あまりゲームには興味ないですが、若い人たちが気軽に戦国武将に興味もってもらえていいですね。
また、中国でも日本の武将ブームだそうです。
2010年06月01日
戦国武将⑤ 仁科盛信 高遠歴史探訪その2

版籍を奉還した高遠藩主の内藤頼直の兜と鎧。

高遠で壮絶な戦いをした武将仁科盛信。
信濃の国に歌われる武将は、木曽義仲とこの仁科盛信(信盛とも書きます)の二人です。信州ゆかりのいきいきと最後まで戦いきって逝った代表的武将です。
1582年織田信長の武田攻め(天目山の戦)では、伊那口から攻めあがってきた織田信忠率いる5万の大軍に対し、高遠城に籠り3千の兵を指揮し勇敢に戦いました。そして、討ち死にしました。享年26歳。
このとき、信忠は盛信に降伏を勧告しました。出仕し忠節を誓うのであれば所領は望みのとおりにするし、黄金百枚を差し上げる、と。ところが、盛信は勧告を拒否しました。不当不義の臆病な輩と同じにしないでもらいたい、と降伏の使いに来た僧侶の耳をそぎ落として追い払ったとされています。高遠城を枕に討ち死にした見事さは、敵である織田方からも、比類なき働き、前代未聞の次第と賞賛されたほどです。最後、自らの腹を十文字に斬り、はらわたを掻き出し投げ捨てて果てたとも伝わっています。
武田一族すら続々と兄勝頼を見捨てる中で、仁科盛信は壮絶な抵抗し、武田家最後の輝きを見せたといえます。
この仁科盛信は、甲斐国、武田晴信(信玄)の五男として生まれました。父、武田信玄が、上杉家へ寝返った信濃国安曇郡(大町地域)の名族、仁科盛政を攻め、自害させました。その後、 父、武田信玄の命により、仁科氏の名跡を継ぎ、森城主となり越後国との国境防備を行なっていました。高遠城が落城し、かつては木曽義仲とともに京に上がり、鎌倉幕府御家人となった名門仁科氏一族は、これで滅びてしまいました。
盛信の子供たちは、生き延びて現在まで子孫は続いています。生き延びる際に、身分証明書として持っていたのが信玄のこの絵だったそうです。

写真資料:伊那市立高遠町歴史博物館
前出関連記事:天下第一の桜 高遠コヒガンザクラ
http://ikiikiikiyou.naganoblog.jp/e458116.html
絵島 高遠歴史探訪その1
http://ikiikiikiyou.naganoblog.jp/e458146.html
2010年04月15日
戦国武将④ 徳川家康

山岡荘八『徳川家康』は日本では、1950年3月の執筆当初からビジネス本としても評判で、経営者虎の巻のような扱われかたをしてロングセラーとなっています。近年、韓国では「大望」という題名で出版され、ベストセラーとなった他、中国でも2007年秋の刊行以来、全13巻計200万部を売るベストセラーになっており、高い評価を得ています。
山岡は第二次世界大戦中、従軍作家として多くの特攻隊員を取材した経験があったそうです。その際に触れた日本の存続や世界平和への祈りを胸に秘めて散っていった彼らの思いを、徳川家康の欲した「泰平」に重ね合わせて描こうとしたようです。山岡は連載を終えた後書きを、自邸内に設けた特攻隊員を祀る「空中観音」小堂で書き記しています。
戦国時代の日本から戦争という文字をなくした日本の偉人として、徳川家康は、描かれています。
私は、漫画版の横山光輝『徳川家康』(コミックス全23巻、講談社漫画文庫全8巻) で、昔読みました。
世の中から、戦さをなくすことが、いかに大変な労力か、家康に学びました。

写真は、徳川家康が関が原大坂の陣に着用し、勝利を収めた幸運の兜と伝えられる歯朶前立兜
人形の伏見屋にて
http://www.fusimiya.net/gogatsu/
2010年04月14日
戦国武将③ 直江兼続

2009年NHK大河ドラマ『天地人』(てんちじん)の主人公。ひたすら利のみを求める戦国時代に、「愛」を重んじ、「義」を貫き通した武将・直江兼続。直江兼続は、関が原の合戦後、数万ともいわれる上杉の家臣や家族と共に米沢に移り住みました。そして、現在の米沢市街地の基礎を築いた人物です。大河ドラマ史上初めて関ヶ原の戦いに敗れた側の武将を描いた作品となりました。

「愛」という字を前立にあしらった兜が兼続所用として米沢市の上杉神社稽照殿に伝わっています。この「愛」の字については、俗説として「仁愛」や「愛民」の精神に由来するとも言われますが、上杉謙信が毘沙門天の信仰を表した「毘」の字を旗印に使用するなど、当時、神名や仏像を兜や旗などにあしらうことは広く一般に行われていたことから、軍神である「愛染明王」または「愛宕権現」を表したものとの理解が大勢です。でも、「愛」という字の意味を、しっかり噛み締めて戦ったはずですよね。

少年時代の直江兼続は上杉謙信のもとで『目先の利に捕らわれず、背筋を伸ばして生きることが ”義”の精神』だと教えられ、義の精神を学んだといいます。
豊臣秀吉は直江兼続を 「天下の政治を安心して預けられるのは兼続など 数人にすぎない」と言ったといいます。よほど人望があり信用の出来る人だったのでしょう。
徳川家康も一目置いていたらしく「長高く、姿容(かたち)美しく、言語清朗なり」と智将として見ていました。
米沢への転封の際に、上杉家は大変な財政難に陥りましたが、兼続は「人こそ組織の財産なり。みんな来たい者はついてこい」といい、召し放ちなどの現代で言うリストラをしなかったといいます。米沢はかつての領国の4分の1の石高の地で、上杉家を待っていたのは厳しい暮らしでした。しかし、兼続はここで家臣と家族3万人を養おうと、自らは質素な暮らしをしながら、国造りに取り組んだのです。米沢市の郊外には、兼続の指示で土地を開いた武士の子孫が今も暮しているそうです、その家の周りには栗や柿そして生垣にはウコギが植えられています。いずれも食べられる食用の木。兼続は実用的な植物を植えさせることで、人々の暮らしの助けになるよう心を配っていたのでしょう。
家の家内アチも、庭には食べられるものを植えてよ、、、とよくいいます。これは、ドケチだからですが、、、(笑)。電源を切ったのに、コンセントまで必ず抜いたり、人のいない部屋に電気をつけていると、小遣い減らすからね、と厳しいアチです。そのくせ、年末には宇宙銀行に預けるといって、多額の寄付をしていたりするので、世のためにケチという、アチでした。私にも、もっと「愛」をチョウダイ!愛って?お小遣い、、、。あげません!
写真は人形の伏見屋にて
http://www.fusimiya.net/gogatsu/case/post-6.php
2010年03月26日
戦国武将② 真田幸村

真田氏といえば「六文銭」の家紋で有名でした。死者が三途の川を渡るときの渡し賃が六文ということから、決死の覚悟でただ全力を尽くすという意味をこめています。
「六文銭」の紋は地蔵信仰による仏教色の強い家紋です。武将は戦で人を殺す、仏教では殺生は許されないことであり、殺生を常とする武将は地獄に落ち、永遠の責め苦に会うにちがいない。でも、修行僧の形をかりてこの世に現れて六道輪廻の周生を救おうとする地蔵の慈悲は、武将の非道を救うとされると信じて、この紋をつけているのでしょう。
滋野氏の家紋の一つが六文銭であり、真田氏の始祖・海野氏、そして真田氏も採用となったとのことです。また「六文銭」の家紋は、江戸時代の軍記物「真田三代記」では、信繁(幸村)の代から使用したという記述がありますが、実際には信繁の祖父・幸隆の頃にはすでに使用されていたといいます。また「六文銭」の家紋は、戦争時に用いられた家紋であったといわれ、平時は結雁金(むすびかりがね)、目出度い時は州浜(すはま)紋を使用したといいます。

大阪夏の陣で信繁(幸村)が赤色で統一した部隊に六文銭の旗をなびかせて、徳川家康の本陣に突入したところ、本陣にいた家康の旗本が恐れをなして、家康を見捨てて逃げ去ってしまった、という有名なエピソードもあります。
真田氏といえば、戦国随一の知恵者といわれています。信州人のさえた頭の侍軍団だったと思います。
でも、単に頭がいいということではなく、とにかく、考えて考えて考えて、一生懸命考えて、全力で知恵を絞ったということだと思います。時は、平成の大不況時代です。皆で、大いに打開策を考えましょう!

人形の伏見屋にて
鎧平飾り 名将真田幸村公鎧:絹金彩屏風飾:翠鳳作
http://www.fusimiya.net/gogatsu/yoroi/post-145.php
2010年03月19日
戦国武将① 伊達政宗

幼少時(5歳)にして患った疱瘡(天然痘)により右目を失明した伊達政宗は、ハンディキャップをかえってトレードマークとして、粋な戦国武将として活躍しました。戦国屈指の教養人として、豪華絢爛を好むことで知られています。
豊臣秀吉や徳川家康に「右目はどうしたのか?」と聞かれた際において、政宗は「木から落ちたとき、右目が出てきてしまったが、あまりに美味しそうだったので、食べてしまった」と語ったそうです。
「伊達男」の名にふさわしく、人に寝姿はみせない、また臨終の際、妻子にも死に顔を見せない心意気であったそうです。
辞世の句は、「曇りなき 心の月を 先だてて 浮世の闇を 照してぞ行く 」
遺訓
一、仁に過ぐれば弱くなる。義に過ぐれば固くなる。礼に過ぐれば諂(へつらい)となる。智に過ぐれば嘘を吐く。信に過ぐれば損をする。
一、気長く心穏やかにして、よろずに倹約を用い金銀を備ふべし。倹約の仕方は不自由なるを忍ぶにあり、この世に客に来たと思へば何の苦しみもなし。
一、朝夕の食事はうまからずとも褒めて食ふべし。元来客の身に成れば好き嫌ひは申されまじ。
一、今日行くをおくり、子孫兄弟によく挨拶して、娑婆の御暇申すがよし。
兜は、三日月型の『弦月』の前立てが、かっこいいですね。
人形の伏見屋にて
銀伊達政宗着用兜:平安清秀作
http://www.fusimiya.net/gogatsu/compact-shuunou/post-131.php